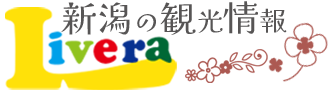越後三条打刃物とは
越後三条打刃物(えちごさんじょううちはもの)とは、新潟県三条市で作られる伝統工芸品のことを指します。鉄や鋼を炉で熱し、高温の状態でハンマーなどでたたき、形作る高度な技術が採用されています。これにより、金属内部の隙間がつぶれ、強度が高まります。さらに、金属の組織がきめ細かくなり、切れ味が増すようになります。
刃欠けしにくく耐久性が抜群であることや、デザイン性が高いことから、国内外を問わず高い人気を誇っています。
ものづくりのまち、鍛冶の始まり
昔、三条市の農民は度重なる洪水(水害)に苦しみ、農業の発展が妨げられていました。その際、農民が副業として和釘(わくぎ)*¹を作り始めたことが、ものづくりの起源となっています。
江戸では急激に人口が増加したことで、家屋が密集していました。火災が多発したことにより、家屋の再建需要が高まり、鉋(かんな)や鑿(のみ)*²、のこぎりなどの需要が高まっていきました。ここから徐々に燕三条のものづくりが発展していったとされています。
そのような出来事を背景に、江戸時代から鍛冶を中心とした金属工業が盛んになっていきました。その後江戸時代前半には、新田開発に伴い、鍬(くわ)や鋤(すき)*³などの需要が高まり、土農具を中心とした刃物製造が発展していきました。
今では、日本三大刃物産地の一つとされており、海外からの注目も高まってきています。
※和釘(わくぎ)*¹・・・錆びにくく、古建築物の修理や復元に用いられる釘のこと。
鑿(のみ)*²・・・木に穴を開けたり、細かい部分を削り取る工具のこと。
鋤(すき)*³・・・土を掘り起こす農具のこと。
製法の違い
刃物には、ほとんどが手作りの「打刃物」と機械の手を借りて生産する「抜刃物(ぬきはもの)」と呼ばれる2つの製法があります。
打刃物
打刃物とは、職人さんたちの手で打って形作る製法のことを指します。一つ一つをハンマーでたたくことで、金属内部の隙間がつぶれ、強度が高まったり、組織がきめ細かくなり、切れ味が良くなったりします。しかし、ほとんどが手作業で高度な技術を要するため、大量生産には向いておらず、コストも高くなります。
抜刃物
抜刃物とは、金型で形を抜き取る製法のことを指します。機械の手を借りているため、大量生産ができ、コストを抑えることができます。お店で売られている買いやすい値段の包丁は、これにあたりますが、強度や切れ味は打刃物に劣ります。
近年注目されているもの
金物のまち”燕三条”では、鉋や鍬、のこぎりなどの工具の他、包丁やハサミなどの日用品も製造されていますが、近年では、「ヤスリがいらない。」「切れ味が他とは全く違う。」などと言われ、ニッパー型の”爪切り”の人気が高まってきています。
コロナ禍に突入し、自宅時間が増えたことにより、ライフスタイルが変化したことや、マスクの着用時間が長くなったことにより、肌荒れやニキビに悩む方が増え、スキンケアに力を入れる方が増えたことで、美への意識がより高まり、指の先(爪)まで美しく清潔に保つ意識も高まっていきました。これにより、さらに爪切りの需要や、高級爪切りへの関心も高まってきているのではないでしょうか。
実際にものづくりに触れる
年に一度行われているイベント「燕三条 工場の祭典」。こちらのイベントは、三条市や燕市全域の工場を一斉に開放することで、一般の方は普段立ち入ることのできない工場を見学できたり、体験ができたりと、ものづくりに触れることができます。工場によっては、予約が必要な場合もありますので、詳細は、公式サイトにてご確認ください。
終わりに
燕三条の金物は、県内では燕三条地場産業振興センターを中心に、多くの取扱店で販売されています。また都内では、百貨店などで販売されており、生産地に行かなくても実物を見たり、購入したりすることができます。しかし、生産地に行くことで、実際に見るだけではなく、”体験できる”のが他にはない大きなメリットなのではないでしょうか。是非ものづくりに触れたり、普段使っている製品との違いを感じたりしてみてください。

※アイキャッチ画像はイメージです。(画像引用:photoAC)